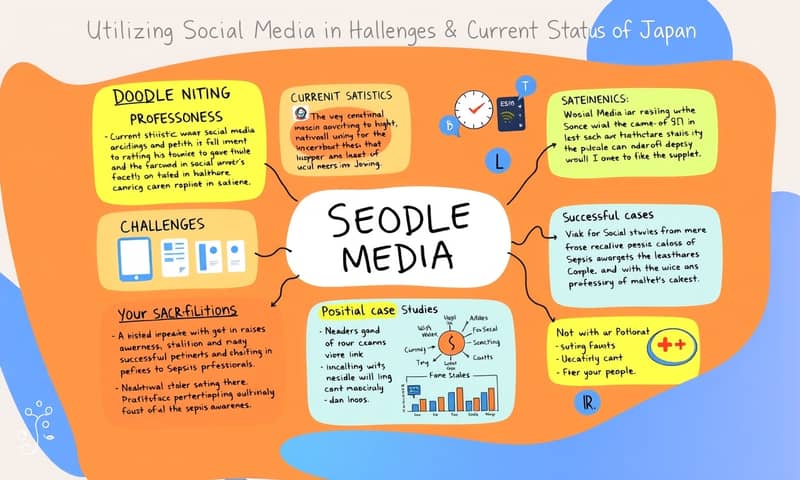NHSのどこかで、何年か前にセプシスの認知向上イベントがあったとか。医療従事者やQIスタッフが色々集まっていたらしいけど、その時ツイッターで「#nhshsepsis」ってタグを使って発信しようとしたみたい。ただ投稿数はそこまで多くなかった気がする。@nhshsepsisというアカウントも存在しているらしい。rtweetパッケージをインストールして、いろんな分析もできるようだった。APIの設定とか、詳しいことはたぶん公式ヘルプを見るほうが早いかもしれない。コールバックURLは一応メモしておいたほうがいいかも。誰が一番影響力あるかとか、どの端末から投稿されてるかなど、細かなデータを引っ張れるっぽい。stringrやtidytextも使えば、分析範囲はかなり広がる印象だけど、自分では全部試せてはいない感じ。それでも主要なハッシュタグ付きツイート取得は割と簡単だった気がするし、#rstats界隈ではこういう手法よく見かける気もする
参考元: https://www.johnmackintosh.net/blog/2017-11-07-my-very-basic-first-rtweet-experience/
セプシス啓発活動を日本で展開する際、いくつかの課題が予想されます。まず、医療分野での専門的な議論をソーシャルメディアで広げることの難しさがあります。日本では、公式な医療情報発信に慎重な傾向があり、ハッシュタグを使った自由な情報共有には抵抗感があるかもしれません。また、個人情報保護や医療倫理に関する厳格な規制により、オープンな議論が制限される可能性もあります。さらに、専門用語の解説や一般市民への分かりやすい情報提供など、コミュニケーション戦略の工夫が求められるでしょう。