ユニットテスト導入で残業・ミス・負担を同時に減らす実践策
- 毎週1回、既存コードの20%以上を単体テスト追加や修正対象に選ぶ
エラー発見率が上がり、予期せぬ障害による急な残業を防げる
- 新しい機能開発時は必ず関数ごとに最低3件のユニットテストを書く
バグ混入リスクを早期低減でき、後から修正する手間も約半分になる
- *push前*に全自動テスト実行し、失敗率10%未満ならデプロイ許可
*手戻り*や深夜対応が減り、開発者の睡眠不足と精神的負荷まで緩和される
- *レガシーコード*にはスプラウトメソッド法で週2つ新規メソッド化してUT追加
直接編集より安全で品質担保しやすく、不具合検知効率も向上する
ユニットテストで防げる深夜の障害と開発コストを抑える方法
嵐が来る前の妙に澄んだ空気、感じたことある?なんとも言えない静けさ――まあ、ああいう瞬間がコードの世界にもあると思う。プログラムが牙を剥く直前って、なぜか小さく「ピリッ」と響いて、それ自体が将来の火種を消してくれる予防テストみたいな存在になる、と私は思っている。 まったく、午前4時だよ……猫のケヴィンが急に大暴れを始めたその時、ノートPCには例の「本番障害」通知ランプがぴこぴこ点滅しだす。欸、不吉なデジャヴってこういうやつかな。不意に襲いかかる空腹と変な脂汗で嫌になる。手元のスプレッドシート上では各種指標が急転直下――夏場に株価大暴落したとき、そのチャートみたいなんだけど……正直見たくもなくなる。有り合わせでも小さいテストさえ用意していれば、この数百時間もの労働も千単位ユーロ損失も、不機嫌なチームとの軋轢も、少しはマシだったよな…って思わされてしまう(毎回)。 いや、ほんと、「これなら多分動くだろう」という油断と、「もう絶対問題なし」と証明された安心感、その間に広大な溝がある。その隙間を埋めるための取り組みこそ、いわゆるユニットテストじゃないかな。新人エンジニアでもプロダクトマネージャーでもSREでもCFOですら――正直、この文化は誰ごとにもできてしまうくらい現実的なもの。
1️⃣ キーボード越しの視界:ゴーストハントから逃げたい一心
なんというか、自分でコード書いている最中は劇作家になった気分になるんだよね。このセリフ(=ロジック)、本当に意味通じてる?それともどっかで噛み合わない部分残してない?全部“筋”通ってほしいと思いながら行単位で眺めている感じ。それなのに、一個関数ミスればポカっとバグ生む危険がつきまとって――不安定なんだ。「ユニットテスト」はそんな時、小声で「ここはOK、大丈夫」って緑色で返事を返してくれる心強いフィードバック装置みたいなもので……どうしたってホッとしてしまう。
学習曲線について
再度コーディングする局面になると、人知れずエラー仕込んだ場合でも即座に察知できる体制だけは守り続けたいと思うわけ(癖というより祈り)。ま、いいか。
1️⃣ キーボード越しの視界:ゴーストハントから逃げたい一心
なんというか、自分でコード書いている最中は劇作家になった気分になるんだよね。このセリフ(=ロジック)、本当に意味通じてる?それともどっかで噛み合わない部分残してない?全部“筋”通ってほしいと思いながら行単位で眺めている感じ。それなのに、一個関数ミスればポカっとバグ生む危険がつきまとって――不安定なんだ。「ユニットテスト」はそんな時、小声で「ここはOK、大丈夫」って緑色で返事を返してくれる心強いフィードバック装置みたいなもので……どうしたってホッとしてしまう。
学習曲線について
再度コーディングする局面になると、人知れずエラー仕込んだ場合でも即座に察知できる体制だけは守り続けたいと思うわけ(癖というより祈り)。ま、いいか。
失敗から学ぶ:素早くフィードバックを得てコード品質を上げる仕組み
短いユニットテストって、本当に結果が出るの、息する間もなくてさ。いやもう、面食らうくらい早いよ。例えばさ、真っ暗な地下室で消えたレゴを手探りで探している感じ…伝わるかな。もしテストなしなら、多分適当に箱を次から次へと開けまくって、結局全然見つからずに終わっちゃうかもしれないんだ。でもテストがあればさ、その場にパッと懐中電灯で一点だけピンスポットが当たるようなもの。三百ミリ秒以内に「ここ引っかかってます」って言われて…あぁなるほど、とすぐ手を止めちゃう。ひとまず、一行サクッと直してまた進む。このやり方だとさ、だらだらしたログの迷宮で道草食うよりも、結局はクリエイティブなことに頭使えるし、不思議なくらい学びやすくなる。毎回ちょっとずつでも成功体験積み重ねて、「どこが回っていて」「どう直したら良かったのか」がなんとなく感覚で身についてくるし…不思議と自信まで湧いてきたりするんだよね。「革新への胆力」?なんとなくだけど、それも得られている気がしてくる。そしてテスト群そのものがコードを覆う保護ネット的存在というか - 磁器の花瓶包むプチプチ梱包材みたいな感じ?ふっと思いつきで大改造しても、このネットワークがバグや破損になりそうな部分を前もってキャッチして守ってくれるんだ。本当に頼れる味方だよ…。ま、いいか。

テストがもたらす安心感と革新への挑戦力を高めるコツ
最近さ、妙に別のアルゴリズムをいじってみたくなるし、なんだかライブラリごと丸っと変えてしまいたい衝動が湧く時がある。昔書いたコードを別の言語で書き直す…とか、ちょっと疲れるけどやっちゃうタイプ。まあ、それもこれもテスト駆動開発(TDD)があるからなのかなあ。あれって、「絶対守らなきゃいけない戒律」っていうより、自分にとっては、高くジャンプするためのトランポリンみたいな存在なんだよね。不思議と、前は普通に動いてる既存コードを触るのがひたすら怖かった。…今では?自分でもびっくりするくらい、「もっと良いやり方」を探そうと積極的になれている気がするんだ。ええと、ほら例のgreen pipes - 変更加える度に全部正常かどうか点検してくれるアレ - のおかげでさ、不安がだいぶ和らぐんだよね。それでついつい創造性というか、実験したい欲求まで膨らんできて。「地雷原でビクビク進む」みたいな緊張感から解放されてる実感、強い。
【メンタルヘルス】この情報洪水時代じゃ、本当に澄み切った頭脳を保つこと自体、ちょっとした贅沢だったりする気もしてきたよ。夜遅く作業エディタ閉じて、ま、その日中にやり残した心配事とか失敗へのモヤモヤ――ベッドまで引きずり込みたくないじゃん。それが意外にもユニットテスト達のお陰というか、「今日書いたコード、この子たち(テスト)が護衛してて安心」って思えるから不思議。そのせいもあってかさ、夜中ふと目覚めても原因は飼猫ケビン(最近またぬいぐるみネズミ無くしがち)が部屋中カサコソ探してる音だけになった。一昔前によく鳴り響いた「本番環境落ちました」と泣き叫ぶような電話……もう最近耳にもしなくなった気がするわ。
【メンタルヘルス】この情報洪水時代じゃ、本当に澄み切った頭脳を保つこと自体、ちょっとした贅沢だったりする気もしてきたよ。夜遅く作業エディタ閉じて、ま、その日中にやり残した心配事とか失敗へのモヤモヤ――ベッドまで引きずり込みたくないじゃん。それが意外にもユニットテスト達のお陰というか、「今日書いたコード、この子たち(テスト)が護衛してて安心」って思えるから不思議。そのせいもあってかさ、夜中ふと目覚めても原因は飼猫ケビン(最近またぬいぐるみネズミ無くしがち)が部屋中カサコソ探してる音だけになった。一昔前によく鳴り響いた「本番環境落ちました」と泣き叫ぶような電話……もう最近耳にもしなくなった気がするわ。
睡眠と集中力が変わる!開発者の心身を守るテスト活用法
質の良い睡眠を取れた朝って、本当に体が軽くなるような気がしない?頭も冴えわたる、というか、不思議と物事に集中できる。とはいえ、全部がいつもうまくいくわけじゃないんだけど…。ちゃんと休息できていると、翌日の作業に対する気力も全然違うし、なんだかケアレスミスも減った気になる。えーっと、やっぱりテストは単なるツールとか仕組みだけじゃなくて、開発してる自分自身や、そのまわりの人々のストレスを少し和らげたり、「まあ何とかなるさ」と思えるくらい生活バランスを支えてくれる…そんな感じで考えてみてもいいのかな。ま、いいか。
2️⃣ テストマネージャーとQAチーム:最初に不協和音を察知するオーケストラ
うーん、この役割は正直オーケストラの指揮者にちょっと似てるんじゃないかなと思っている。各パート(それぞれがアプリ内要素)には個別にマイクが付いていて、ユニットテストは…そうだな、バイオリンパートと言えばぴったりくるかもしれない。目立つようで実際は縁の下の力持ち―あれが抜け落ちればシンフォニー自体ガタガタになってしまうからね。それにピラミッド効果?これはLEGOブロック積む感覚にも近しいよなあ。土台広めでごつく安定、一番上は意外と細身だったりして。仮にその土台部分でヒビを見つけたら、即座に取り替えて補強することで塔全体の「倒れそう」な雰囲気を消すこともできたりして…こういう柔軟な対応こそ大事なのかもしれないね。
2️⃣ テストマネージャーとQAチーム:最初に不協和音を察知するオーケストラ
うーん、この役割は正直オーケストラの指揮者にちょっと似てるんじゃないかなと思っている。各パート(それぞれがアプリ内要素)には個別にマイクが付いていて、ユニットテストは…そうだな、バイオリンパートと言えばぴったりくるかもしれない。目立つようで実際は縁の下の力持ち―あれが抜け落ちればシンフォニー自体ガタガタになってしまうからね。それにピラミッド効果?これはLEGOブロック積む感覚にも近しいよなあ。土台広めでごつく安定、一番上は意外と細身だったりして。仮にその土台部分でヒビを見つけたら、即座に取り替えて補強することで塔全体の「倒れそう」な雰囲気を消すこともできたりして…こういう柔軟な対応こそ大事なのかもしれないね。

チーム全体の品質向上へ導くQA文化の育て方
ユニットテストって、実はけっこう地味だけど大切なんだよね。問題が起こったとき、その発生源ですぐに見つけ出せるのがポイントでさ、直すのも正直数分で済んじゃうことがほとんど。ただね、統合テストとかエンドツーエンドテストになると話は全然変わる。あの辺りってピラミッドで言えばずっと上層になるし、データベースだったりネットワークだったり、それにユーザーインターフェースみたいな部分まで絡んできてさ、既にいろんな要素がゴチャッと連動している段階。
ここでバグ修正ってなるともう一苦労で…複雑性もコストも跳ね上がるんだよ。下手すると何人もの担当者が集まって相談しないと対策打てないし。えーと、なんというか…イメージ的には屋外フェスティバルでフィルハーモニー管弦楽団が演奏してるようなものかもしれない。一曲だけでもトラブルが出ちゃえばさ、ステージ組立から音響や照明の調整、それにチューニングとか――それら全部を準備し直すためにめちゃくちゃ時間もコストも掛かる感じ?(うーん…本当悩ましいよね)
あと、「シグナル・トゥ・ノイズ比」についてなんだけど―これはつまり、ノイズだらけの状況下でも本当に必要な情報や事実をどれくらいクリアに掴めるか…そういう度合いを示す指標だったりするわけ。ま、この表現自体ちょっと理系っぽくて好きなんだけど。(ふぅ…説明って意外に難しいよね。)
ここでバグ修正ってなるともう一苦労で…複雑性もコストも跳ね上がるんだよ。下手すると何人もの担当者が集まって相談しないと対策打てないし。えーと、なんというか…イメージ的には屋外フェスティバルでフィルハーモニー管弦楽団が演奏してるようなものかもしれない。一曲だけでもトラブルが出ちゃえばさ、ステージ組立から音響や照明の調整、それにチューニングとか――それら全部を準備し直すためにめちゃくちゃ時間もコストも掛かる感じ?(うーん…本当悩ましいよね)
あと、「シグナル・トゥ・ノイズ比」についてなんだけど―これはつまり、ノイズだらけの状況下でも本当に必要な情報や事実をどれくらいクリアに掴めるか…そういう度合いを示す指標だったりするわけ。ま、この表現自体ちょっと理系っぽくて好きなんだけど。(ふぅ…説明って意外に難しいよね。)
レゴブロック型テストピラミッドで効率よく不具合検知する手順
ユニットテストがパタリと落ちる瞬間、やけにハッキリしたメッセージが出るんだよね。「こんな細かいところで、誰かがほんの一文字ぽろっと忘れてた」ってさ。ま、いいか。でも十八ものマイクロサービスを渡り歩きながらエラー原因を探し回る羽目にはならなくて、テストがピンポイントで「ココだよ!」と教えてくれる。それって意外と救いなんだけど…。うーん、その逆でエンドツーエンドテストのシナリオが失敗するとなると、それはもう…コンサートホールで急に何か音がズレて、おいおい何が悪さしてるかわからず楽器ひとつずつチェックしないといけない状況、あれによく似てる気がして(ため息)。演奏者はしかめ面で手元を見つめ直して、観客はだんだんソワソワして待ちきれなくなる。その光景、想像つくだろ?
品質文化っていうやつもさ、「QAチーム=警察」みたいな役割感からじわじわ形を変えて発展していくもんなんじゃないかなと思ったりする。話戻すけど―開発者にユニットテスト書こうぜって背中押すテスターは、「監視する人」よりむしろ「一緒に公園で遊ぶ仲間」になれる感じ。プログラマーたちは誰かに見張られる存在じゃなくて、自分自身の演奏をこっそり聴き返したり、本番前の静かな試験室でこっそりデバッグ道具扱えるようになるって寸法だ。QA担当は自分なりの経験談やヒントを惜しまず差し出しながら、一番イケてそうなルートへの案内人でもあるわけだよね。この方法によって、「ダメ出しくらいたくない」って防御ばっか考えちゃう姿勢から、「最初っからバッチリ決めてやろう」という攻めモードへの切替え…まあ、不思議と生まれてくるものだった。
品質文化っていうやつもさ、「QAチーム=警察」みたいな役割感からじわじわ形を変えて発展していくもんなんじゃないかなと思ったりする。話戻すけど―開発者にユニットテスト書こうぜって背中押すテスターは、「監視する人」よりむしろ「一緒に公園で遊ぶ仲間」になれる感じ。プログラマーたちは誰かに見張られる存在じゃなくて、自分自身の演奏をこっそり聴き返したり、本番前の静かな試験室でこっそりデバッグ道具扱えるようになるって寸法だ。QA担当は自分なりの経験談やヒントを惜しまず差し出しながら、一番イケてそうなルートへの案内人でもあるわけだよね。この方法によって、「ダメ出しくらいたくない」って防御ばっか考えちゃう姿勢から、「最初っからバッチリ決めてやろう」という攻めモードへの切替え…まあ、不思議と生まれてくるものだった。
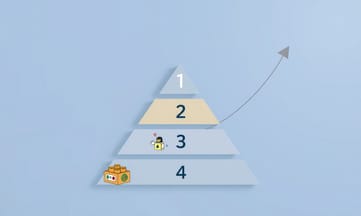
単体テストでエラー箇所を特定しやすくするアプローチとは?
IBMが示した調査によれば、本番環境でバグを発見した場合、それを単体テストで見つけていたときに比べて平均して100倍ものコストが生じるとのことなんですよね(出典:IBM)。ま、ここは結構企業ごとに幅もあるとは思うんだけど...数字としてこの傾向、概ね変わらないのが妙なリアリティというか。もう少し噛み砕くとさ、直接的にはロールバックや緊急修正、お客さんへの補償とか…いろいろ即時対応が必要になってくるし。その裏側では評判低下やユーザー離脱だとか、計画遅延など目に見えにくいダメージもしっかり出てくるんだよな。あー、機会損失とか完全に無視できない話だから、本当に参る。
たとえばCFOだったらどうなんだろう――ユニットテスト?まあ観葉植物みたいな存在って思う人もいるかな。ほら、オフィスでは美しいけど正直なくても困らなそう、と。でもね…実際には成長中の車に取り付けるシートベルトそのものと言えるんじゃないかって、私は感じちゃう。確かにテスト導入にも一定の時間やお金がかかるのは事実。でも一度でもその「安全装置」がない状況で何か事故ったら…想像以上に痛烈な結果を招くだろうし、それこそ再起不能ってパターンすら有り得なくはない気がする。ま、いいか。
たとえばCFOだったらどうなんだろう――ユニットテスト?まあ観葉植物みたいな存在って思う人もいるかな。ほら、オフィスでは美しいけど正直なくても困らなそう、と。でもね…実際には成長中の車に取り付けるシートベルトそのものと言えるんじゃないかって、私は感じちゃう。確かにテスト導入にも一定の時間やお金がかかるのは事実。でも一度でもその「安全装置」がない状況で何か事故ったら…想像以上に痛烈な結果を招くだろうし、それこそ再起不能ってパターンすら有り得なくはない気がする。ま、いいか。
修正工数や金額ダウン:経営目線で考えるユニットテストの意義
本番環境でバグが滑り込んだら、まあ、本当に困るんだよね。そういう時は即座に直接費用が生まれてしまう。チームは突然「ロールバック」せざるを得ないってわけさ──つまり、つい先ほどまで頑張っていた変更を、あっさりと元に戻す羽目になる。それだけじゃない。リリース中止の宣言、データベースの状態確認、それから不具合抜きのパッケージを再び作成し直す面倒も待っている。ふう…なんでこうなるのか、自分でも時々悩むよ。
そして、その後も一息つける暇なんてほぼ無し。今度はホットフィックススプリント、要するに緊急修正対応ってやつが始まるわけ。でも、ただ開発者同士でブツブツ言い合うだけでなく、誰かが必ず予定を全部キャンセルしてまで現場に残り、「何とかしてサービスを復旧させなきゃ」と大慌てになること多し。その流れで顧客への補填まで出てくる……割引や返金、とりあえず謝罪の意味でクレジット進呈とか。仕方ないとはいえ、本当ため息しか出てこない。
結局、この連鎖反応みたいなステップ全部が作業時間も実際のお金も会社から吸い取ってしまう感じだ。それくらいコストとして見えてくるし計測もしやすいので、とにかく一気に増えるものなのだよ。あー…ちょっと考えたくもなくなるな、ほんと。ま、いいか。
そして、その後も一息つける暇なんてほぼ無し。今度はホットフィックススプリント、要するに緊急修正対応ってやつが始まるわけ。でも、ただ開発者同士でブツブツ言い合うだけでなく、誰かが必ず予定を全部キャンセルしてまで現場に残り、「何とかしてサービスを復旧させなきゃ」と大慌てになること多し。その流れで顧客への補填まで出てくる……割引や返金、とりあえず謝罪の意味でクレジット進呈とか。仕方ないとはいえ、本当ため息しか出てこない。
結局、この連鎖反応みたいなステップ全部が作業時間も実際のお金も会社から吸い取ってしまう感じだ。それくらいコストとして見えてくるし計測もしやすいので、とにかく一気に増えるものなのだよ。あー…ちょっと考えたくもなくなるな、ほんと。ま、いいか。
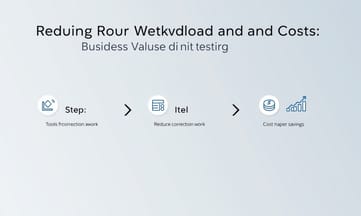
サービス信頼性や成長スピード維持に役立つ間接費用対策とは
間接的なコスト…なんだろうね、これ。まあ正直、ミスってすぐにエクセルとかスプレッドシートに表れなくても、その余波はじわじわ効いてくる気がするんだよね。たとえばサービスが一旦止まっちゃったりするとさ、「ああ、もう信用できないな」って思う人も当然いるわけで。ユーザーの中には、そのまま別の会社やサービスへ移っちゃって、結局戻ってこないケースもあるんじゃないかって想像しちゃう。
それにさ、もしメディアなんかで今回の障害を大きく取り上げられたりした場合…問題自体は数時間で解決しても、「あの会社、一回やらかしたよね」みたいな印象が尾を引いちゃうことも多々ある。意外と痛手が長引いたりするよなぁ…。あと、危機対応してる最中は本来やる予定だったタスクを全部一旦棚上げするから、プロジェクト全体の進行表にもズレが出てくる。それで新しい機能リリースとかも後ろ倒しになるし、「この会社最近ぜんぜん動きなくない?」って見え方をされても無理はない。ぱっと見では分かりづらい損失だけど、それこそ雪玉転がすみたいに後になればなるほど膨らんでいきそう…ふぅ。
さらにオポチュニティコストという観点から言うとね、チーム全員が障害対応に追われてる間、新しい価値を生み出せる日は確実に減っちゃう。ほんとは新機能考案したかったりパフォーマンス良くしたかったりなのに、ただひたすらバグ修正とログ漁りの日々…「何やってるんだろ、自分」とモヤモヤする瞬間もちょっとある(笑)。その間にも他社がどんどん新しい要素追加して、市場シェア伸ばしかねない現実…。いや~厳しい世の中だ、とつくづく思ったよ。
それにさ、もしメディアなんかで今回の障害を大きく取り上げられたりした場合…問題自体は数時間で解決しても、「あの会社、一回やらかしたよね」みたいな印象が尾を引いちゃうことも多々ある。意外と痛手が長引いたりするよなぁ…。あと、危機対応してる最中は本来やる予定だったタスクを全部一旦棚上げするから、プロジェクト全体の進行表にもズレが出てくる。それで新しい機能リリースとかも後ろ倒しになるし、「この会社最近ぜんぜん動きなくない?」って見え方をされても無理はない。ぱっと見では分かりづらい損失だけど、それこそ雪玉転がすみたいに後になればなるほど膨らんでいきそう…ふぅ。
さらにオポチュニティコストという観点から言うとね、チーム全員が障害対応に追われてる間、新しい価値を生み出せる日は確実に減っちゃう。ほんとは新機能考案したかったりパフォーマンス良くしたかったりなのに、ただひたすらバグ修正とログ漁りの日々…「何やってるんだろ、自分」とモヤモヤする瞬間もちょっとある(笑)。その間にも他社がどんどん新しい要素追加して、市場シェア伸ばしかねない現実…。いや~厳しい世の中だ、とつくづく思ったよ。
小さな予防で企業価値とチームワークを守る実践ポイント
機会損失ってさ、なんだか大層な言葉に聞こえるけど、現状を守ることばっかに夢中になった挙句、本来ゲットできてたはずの収入や成果をごそっと手放しちゃう、そんな皮肉な結果のことだったりする。言ってみれば、これって単なる帳簿上の数字なんかじゃなくて、市場がえらいスピードで進化している真っ只中、自分たちだけが後ろ向きに漂流している……そんな本当の意味で「遅れ」なのかも。実感湧くような話…では?
### 結論
いやあ、この前夜中にうちの猫――名前?別に秘密でもないけど――がレーザーポインターを夢中で追い回す姿をぼんやり見ていたんだよね。その様子が何となく予防的投資のイメージと重なった気がした。一緒にほんの数分じゃれてやるだけで、MacBook のケーブル食い千切られるみたいな災難も防げたりするわけ。ま、それだけ。
この感覚と似ていてさ、ごく短めなユニットテスト一発書くだけで、「無駄すぎるケーブル再購入プロジェクト」みたいなのをごっそり減らせたりしちゃうから面白い(経験あるよ…。)。そのおかげでチームのみんなも、腹いっぱいになって満足そうな猫よろしく安眠できるんだ。ユニットテストってさ、管理チェックというより実は開発者にもマネージャーにも、その果てには会社経理担当者まで巻き込んで「安心」と「創造性」、ついでに「信頼」を得るためへの“投資”として働くものなんだと思う。本当に。
問題点がまだ微かな鳴き声(mewl)レベルの段階できちんと察知できれば、生産環境というジャングルでトラブル炸裂(roar!)になる前にどうにか対応間に合うし。その意味でも、次もし小さいヘルパーメソッドとかテスト書くべきかモヤッと悩む時はさ、「Kevin のコード上の鳴き声」が頭によぎったなら、その瞬間だけちょっと手を動かしてみてほしいと思うんだ。未来への安堵も会社のお財布事情も……それどころか私のボロボロケーブルですら救われる日が来る――なんて妄想してたりする。ま、いいか。
### 結論
いやあ、この前夜中にうちの猫――名前?別に秘密でもないけど――がレーザーポインターを夢中で追い回す姿をぼんやり見ていたんだよね。その様子が何となく予防的投資のイメージと重なった気がした。一緒にほんの数分じゃれてやるだけで、MacBook のケーブル食い千切られるみたいな災難も防げたりするわけ。ま、それだけ。
この感覚と似ていてさ、ごく短めなユニットテスト一発書くだけで、「無駄すぎるケーブル再購入プロジェクト」みたいなのをごっそり減らせたりしちゃうから面白い(経験あるよ…。)。そのおかげでチームのみんなも、腹いっぱいになって満足そうな猫よろしく安眠できるんだ。ユニットテストってさ、管理チェックというより実は開発者にもマネージャーにも、その果てには会社経理担当者まで巻き込んで「安心」と「創造性」、ついでに「信頼」を得るためへの“投資”として働くものなんだと思う。本当に。
問題点がまだ微かな鳴き声(mewl)レベルの段階できちんと察知できれば、生産環境というジャングルでトラブル炸裂(roar!)になる前にどうにか対応間に合うし。その意味でも、次もし小さいヘルパーメソッドとかテスト書くべきかモヤッと悩む時はさ、「Kevin のコード上の鳴き声」が頭によぎったなら、その瞬間だけちょっと手を動かしてみてほしいと思うんだ。未来への安堵も会社のお財布事情も……それどころか私のボロボロケーブルですら救われる日が来る――なんて妄想してたりする。ま、いいか。



