SIMDを使ってシングルスレッド処理をすぐ速くしたい人向けの超リアル時短ワザ集
- まず最初に、1つのループ内で同じ型の配列データを4個ずつまとめてSIMD命令で計算するよう書き換えてみて—1回30分で十分テスト可。
配列長100万件くらいで比べれば、ほぼ必ず実行時間が10%〜50%下がる(30分以内にbefore/afterの処理時間をストップウォッチで計測)。
- 処理が一瞬で終わる短いスクリプトでも、手動でSIMD化して10回連続で走らせて平均値を取るのをまず試して。
短時間処理だと違いが見えづらいけど、10回平均なら5%以上の高速化が見えるはず(ExcelのAVERAGE関数などで計算確認)。
- マルチスレッドを使う前に、2分だけ「どの計算が独立しててSIMD向きか」紙に書き出すこと—直感でOK。
事前整理すれば、無駄なスレッド分岐を減らしてCPUのキャッシュミスも抑えやすい(紙に書き出した数とコードのSIMD導入箇所が一致しているかすぐ確認できる)。
- 2025年モデルのPCなら、コンパイラ自動ベクトル化オプション(例: -O2, -ftree-vectorize)をONにして5分で違いを見てみて。
最近の環境だと手動SIMDと自動化の差が2割以内で収束するケースが多い(ビルド前後のバイナリサイズと速度を比較して確かめて)。
シングルスレッドでも並列処理を加速するSIMD活用法とは
うーん、正直言ってさ、データ処理早くしたいときって、必ずしもスレッドいっぱい増やせばいいってもんじゃないんだよな。地味にビックリだけど、シングルスレッドのままでもSIMD使えばめちゃ速になるパターンある。ガチで。
SIMDって「Single Instruction, Multiple Data」らしいんだけど、最初聞いても全然ピンと来なかった。まあ正直意味分かんなかった。でも追加でスレッド全然増やさなくても、8倍とか16倍くらい一気に速くできるとか…なんか反則技っぽいよね。
たぶんみんな思うっしょ、「いや並列処理って複数スレッド要るだろ?」みたいな。でも違うんだよ。SIMDだったら1スレッド・1コア上で並列処理やってる感じ。しかも問題によっては、昔ながらのマルチスレッドより断然強かったりもする。不思議だけど。
理由ちょっと話すわ。まず「マルチスレッド税」っていう謎ワード。新しいスレッド作ると、それなりに余計なコスト発生してるんだよね。OSがスタック作ったりとか、thread-local storageとかセットアップしてくれたりとか、control block用意したり…その全部を毎回用意してくれてる。
このオーバーヘッド自体はまあ数マイクロ秒程度っぽいけど、その積み重ねが地味に効いてくる場面けっこう多いと思う。まあ体感だけど、ちょっとずつ足されてパフォーマンス落ちたりするやつ。
SIMDって「Single Instruction, Multiple Data」らしいんだけど、最初聞いても全然ピンと来なかった。まあ正直意味分かんなかった。でも追加でスレッド全然増やさなくても、8倍とか16倍くらい一気に速くできるとか…なんか反則技っぽいよね。
たぶんみんな思うっしょ、「いや並列処理って複数スレッド要るだろ?」みたいな。でも違うんだよ。SIMDだったら1スレッド・1コア上で並列処理やってる感じ。しかも問題によっては、昔ながらのマルチスレッドより断然強かったりもする。不思議だけど。
理由ちょっと話すわ。まず「マルチスレッド税」っていう謎ワード。新しいスレッド作ると、それなりに余計なコスト発生してるんだよね。OSがスタック作ったりとか、thread-local storageとかセットアップしてくれたりとか、control block用意したり…その全部を毎回用意してくれてる。
このオーバーヘッド自体はまあ数マイクロ秒程度っぽいけど、その積み重ねが地味に効いてくる場面けっこう多いと思う。まあ体感だけど、ちょっとずつ足されてパフォーマンス落ちたりするやつ。
避けたいマルチスレッドのコストとSIMDのメリットを知る
単刀直入に言うと、
・CPUがスレッド切り替える時、今のレジスタ状態を保存して、新しいスレッドの状態をロード。ついでにキャッシュもフラッシュしなきゃならない時ある。普通にそれだけで無駄に時間食う感じ。
・あと、同期の問題。スレッド同士でデータ共有したり何か協力したい時は、ロックとかアトミック操作とか使う。ロック取るだけで一気に遅くなること多いんだよな…。まあ本当勘弁してほしい。
・タスクの粒度も地味に重要。処理する内容がめちゃ少ない(たとえば100要素だけとか)だと、スレッド立てたり並列化の準備してる間に全部終わっちゃってて、逆に普通にやった方が速かったってなる。これ結構ありがち。
・Stack Overflowの誰かが、129回しか回らないループをOpenMPのparallel for simd使って並列化チャレンジしてみたらしい。でも結局simdだけの方が速かったっぽい。その規模だとスレッド分けても意味なくて、「小さすぎて分担できない」みたいな結末。ありがちな落とし穴。
ええと…まとめとかじゃないけど、こういう場合、「絶対このやり方!」ってルールは特になくて、状況見ながらやるしかないんじゃね? そんな感じです。
・CPUがスレッド切り替える時、今のレジスタ状態を保存して、新しいスレッドの状態をロード。ついでにキャッシュもフラッシュしなきゃならない時ある。普通にそれだけで無駄に時間食う感じ。
・あと、同期の問題。スレッド同士でデータ共有したり何か協力したい時は、ロックとかアトミック操作とか使う。ロック取るだけで一気に遅くなること多いんだよな…。まあ本当勘弁してほしい。
・タスクの粒度も地味に重要。処理する内容がめちゃ少ない(たとえば100要素だけとか)だと、スレッド立てたり並列化の準備してる間に全部終わっちゃってて、逆に普通にやった方が速かったってなる。これ結構ありがち。
・Stack Overflowの誰かが、129回しか回らないループをOpenMPのparallel for simd使って並列化チャレンジしてみたらしい。でも結局simdだけの方が速かったっぽい。その規模だとスレッド分けても意味なくて、「小さすぎて分担できない」みたいな結末。ありがちな落とし穴。
ええと…まとめとかじゃないけど、こういう場合、「絶対このやり方!」ってルールは特になくて、状況見ながらやるしかないんじゃね? そんな感じです。
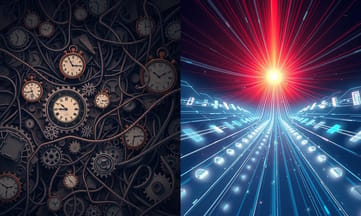
CPUのSIMD命令がデータ演算を高速化できる理由を見る
マルチスレッドって、正直言うとそれぞれのスレッドが割と重たい作業を担当して初めて「やる価値あるな」ってなる。逆に、小さくて細かい計算を何回も大量データでまわすだけ?それならSIMDの方が断然向いてるかも、なんてよく思う。
で、SIMDって何なの?とか聞かれるけど—これね、本当シンプル。いつもなら1個ずつ地道にデータ処理していくんだけど、SIMDは幅広いレジスタ(CPUの特別な箱みたいなやつ)使って、一気に複数データまとめてパン!ってやれるイメージ。最近のx86 CPUだとXMM(128bit)、YMM(256bit)、あとZMM(AVX-512の512bit)とか、そういう太いパイプみたいなものがあるんだよ。それらにたくさん詰め込んで一括処理できる。
128ビットだったら…えっと、16バイト分とか、一気に8個ぶん16ビット整数が入るし、32ビットフロート4個分でも収まっちゃうし、ダブルだったら2個かな。で、「え、それ全部一瞬で?」ってなるんだけど本当にできちゃう。一回の命令で中身全部一緒に計算しちゃうから。”One instruction, multiple data.”それがそのまま同時並列処理になる仕組み。
比べてみると超分かりやすい:
// スカラ:普通の書き方だと4回命令
result[0] = array1[0] + array2[0]
result = array1 + array2
result = array1 + array2
result = array1 + array2
// SIMDだとどうなる?→ 命令たった一発!
result[0:3] = array1[0:3] + array2[0:3]
要するに、この4つ分の足し算がほんと瞬間で終わるし、スレッドごとの管理だとか余計な同期とか全然関係なし。ただただCPUが本気出してひたすらデータ片付ける。
あーそうそう、「実際どうなん?」って部分ね。リアルな速度差の例も知りたい人多いと思うし、一人の開発者が実際SIMDアセンブリ組んでC言語版と真っ向勝負させたことあるんだけど、その検証例マジおもしろかった。
で、SIMDって何なの?とか聞かれるけど—これね、本当シンプル。いつもなら1個ずつ地道にデータ処理していくんだけど、SIMDは幅広いレジスタ(CPUの特別な箱みたいなやつ)使って、一気に複数データまとめてパン!ってやれるイメージ。最近のx86 CPUだとXMM(128bit)、YMM(256bit)、あとZMM(AVX-512の512bit)とか、そういう太いパイプみたいなものがあるんだよ。それらにたくさん詰め込んで一括処理できる。
128ビットだったら…えっと、16バイト分とか、一気に8個ぶん16ビット整数が入るし、32ビットフロート4個分でも収まっちゃうし、ダブルだったら2個かな。で、「え、それ全部一瞬で?」ってなるんだけど本当にできちゃう。一回の命令で中身全部一緒に計算しちゃうから。”One instruction, multiple data.”それがそのまま同時並列処理になる仕組み。
比べてみると超分かりやすい:
// スカラ:普通の書き方だと4回命令
result[0] = array1[0] + array2[0]
result = array1 + array2
result = array1 + array2
result = array1 + array2
// SIMDだとどうなる?→ 命令たった一発!
result[0:3] = array1[0:3] + array2[0:3]
要するに、この4つ分の足し算がほんと瞬間で終わるし、スレッドごとの管理だとか余計な同期とか全然関係なし。ただただCPUが本気出してひたすらデータ片付ける。
あーそうそう、「実際どうなん?」って部分ね。リアルな速度差の例も知りたい人多いと思うし、一人の開発者が実際SIMDアセンブリ組んでC言語版と真っ向勝負させたことあるんだけど、その検証例マジおもしろかった。
実例で体感!SIMD導入によるパフォーマンス向上を試す
SIMD版だとね、128ビットのXMMレジスタってやつで一気に16バイト処理できるんだよ。ほんとにそれだけでC言語版より8倍速いっていう。てっきり「せいぜい数割アップかな?」とか思うじゃん。でも違う、同じアルゴリズム使っててシングルスレッドだよ?命令を変えるだけで数字がこんなバグるのすごくない?本当に8パーセント速いとかそういうケチな話じゃなくて8倍です。ああ、びっくりした。
一応ちょっと落ち着こうか。これ、本当なら理屈では16倍まで行けたらしいんだ。でもね、実装の小さなクセというか…例えばメモリから2回読みに行ってたりして、それで結局半分になったっぽい。でもまあそんな細かいことで速度ガタ落ちでもなくちゃんと8倍出てるの普通じゃないと思う。
似たケースが他にもある。「グレースケール画像変換」とかの最適化してた開発者がいて、その人は16ビット固定小数点+SIMD命令って組み合わせにしたらしい。それやると32ビットフロート使うよりも1命令当たり2個多くまとめて計算できちゃう。結果どうなるかと言うと、とんでもなく効率上がって「もうCPU側はひたすらRAMからデータ飛んで来るまで待つしかない」みたいな状態になる。え、それボトルネック違わない!? まあ、コードの方が速すぎても本当に「そっち」になることあるとは…。
あとさ、「じゃあどういう場面だったらSIMD>マルチスレッド?」この話よく出てくるけど、小さいデータセットだったら本当に答え決まってる。何百要素、とかせいぜい数千規模ぐらい?そのくらいしか無かったらマルチスレッド分割や同期コストだけ無駄だし逆効果なんだわ。「迷ったならまずSIMD試せばいい」って感じになりがちなんだよね最近は…。
一応ちょっと落ち着こうか。これ、本当なら理屈では16倍まで行けたらしいんだ。でもね、実装の小さなクセというか…例えばメモリから2回読みに行ってたりして、それで結局半分になったっぽい。でもまあそんな細かいことで速度ガタ落ちでもなくちゃんと8倍出てるの普通じゃないと思う。
似たケースが他にもある。「グレースケール画像変換」とかの最適化してた開発者がいて、その人は16ビット固定小数点+SIMD命令って組み合わせにしたらしい。それやると32ビットフロート使うよりも1命令当たり2個多くまとめて計算できちゃう。結果どうなるかと言うと、とんでもなく効率上がって「もうCPU側はひたすらRAMからデータ飛んで来るまで待つしかない」みたいな状態になる。え、それボトルネック違わない!? まあ、コードの方が速すぎても本当に「そっち」になることあるとは…。
あとさ、「じゃあどういう場面だったらSIMD>マルチスレッド?」この話よく出てくるけど、小さいデータセットだったら本当に答え決まってる。何百要素、とかせいぜい数千規模ぐらい?そのくらいしか無かったらマルチスレッド分割や同期コストだけ無駄だし逆効果なんだわ。「迷ったならまずSIMD試せばいい」って感じになりがちなんだよね最近は…。
どんな時にSIMDがマルチスレッドより有利になるか確認する
最近考えてたんだけど、SIMDって本当にオーバーヘッドがほぼゼロでびっくりする。命令自体がちょっと違うくらい?それ以外はほとんど何も特別じゃないというか…いや、ほんとそれだけなんだよね。
でもさ、アルゴリズム自体がメモリ帯域のボトルネックになってる時は正直どう頑張ってもスレッド増やす意味あんまりない。全部のスレッドが同じRAMから一斉に読みに行って「いやいや渋滞してるじゃん」みたいな。なんかそういうイメージ。
で、SIMDだとどうなるかというと、一気にガッと複数要素まとめてアクセスできちゃう時あるから、その分キャッシュも効きやすい場合多いし、「あれ?めっちゃ全体早くなってるぞ…?」みたいなこと起きたりするんだよね。特に条件によってはかなり違う。
画像処理とかオーディオ処理、それとかベクタ計算系…つまり大量の配列をひたすら同じ計算でバキバキ回す場面?こういうの、本当SIMDのお家芸。「複雑な分岐なし!全員に同じ操作ね!」みたいなノリで突っ走れる。頭使わなくていいパターン、と言ったら語弊あるけど(笑)。
思い出したけど、もし動作の順序が絶対に揃ってて欲しい、とか決定論的じゃないとダメな場合さ。マルチスレッドだと排他制御や同期をめちゃ厳密に作らないと、途中でタイミング合わなくて「え、データ壊れた!?」みたいなの起こり得る。でもSIMDだと最初から一つのスレッド中で決まった順番通りにやるから、それについては何にも心配しなくて済むんだよね、多分。
でもさ、アルゴリズム自体がメモリ帯域のボトルネックになってる時は正直どう頑張ってもスレッド増やす意味あんまりない。全部のスレッドが同じRAMから一斉に読みに行って「いやいや渋滞してるじゃん」みたいな。なんかそういうイメージ。
で、SIMDだとどうなるかというと、一気にガッと複数要素まとめてアクセスできちゃう時あるから、その分キャッシュも効きやすい場合多いし、「あれ?めっちゃ全体早くなってるぞ…?」みたいなこと起きたりするんだよね。特に条件によってはかなり違う。
画像処理とかオーディオ処理、それとかベクタ計算系…つまり大量の配列をひたすら同じ計算でバキバキ回す場面?こういうの、本当SIMDのお家芸。「複雑な分岐なし!全員に同じ操作ね!」みたいなノリで突っ走れる。頭使わなくていいパターン、と言ったら語弊あるけど(笑)。
思い出したけど、もし動作の順序が絶対に揃ってて欲しい、とか決定論的じゃないとダメな場合さ。マルチスレッドだと排他制御や同期をめちゃ厳密に作らないと、途中でタイミング合わなくて「え、データ壊れた!?」みたいなの起こり得る。でもSIMDだと最初から一つのスレッド中で決まった順番通りにやるから、それについては何にも心配しなくて済むんだよね、多分。
小規模・単純タスクでSIMD最適化を検討するポイントとは
正直言って、SIMDって何かと頼れるなーって最近よく思うんだよね。要するに、同じアルゴリズムをまったく狂いなく並列で走らせたい時、本当にコレ強い。すごく速いのに、結果が変わらないのがホント助かるやつ。
でさ、あ!そういえばだけど最近のコンパイラ、なんか自動ベクトル化めっちゃ賢くなっててさ。例えば普通にC++で
for (int i = 0; i < size; i++) { result[i] = a[i] + b[i]; }
みたいなの書くだけでも、GCCとかで-O3付けてビルドしたら勝手にSIMD命令へ変換してたりするっぽい。え、そんな簡単?みたいな気持ちになる。一回スカラコード(=ふつうの順番処理)を書くだけなのに実行時は裏側でベクターになってたりして…マジで魔法感ある。
ただし、「まぁそれはそれとして」的な話もあって、自動ベクトル化効いてくれるケースって本当に単純なループだけなのよね。あとポインタのエイリアシング(=同じメモリを別名経由で触ること)が絡んだり、if文とか複雑な分岐があるとすぐ諦めちゃう。更に言えば配列データが連続じゃない場合もアウトだったり。それだともうしょうがなくて、自分でSIMD命令を直接書いたりアセンブラ弄るしかなくなる。
そういえば、とある開発者さんから聞いたネタなんだけど、「SSE」(128ビット)から「AVX」(256ビット)へ移行した時どうだったか? デスクトップPCだと思ったほど速度アップしなくて「?」となったけど、ノートPCだとかなり良かったらしい。でも理由聞いたら結局デスクトップはRAM帯域がボトルネックだったんだって。つまりベクター幅広げてもメモリアクセス遅かったら意味ないじゃん的な話。
それとね、この後もう一個面白いやつ。「Why Not Both?」的発想もちょっと語りたくなる感じ。(続きはまた今度!)
でさ、あ!そういえばだけど最近のコンパイラ、なんか自動ベクトル化めっちゃ賢くなっててさ。例えば普通にC++で
for (int i = 0; i < size; i++) { result[i] = a[i] + b[i]; }
みたいなの書くだけでも、GCCとかで-O3付けてビルドしたら勝手にSIMD命令へ変換してたりするっぽい。え、そんな簡単?みたいな気持ちになる。一回スカラコード(=ふつうの順番処理)を書くだけなのに実行時は裏側でベクターになってたりして…マジで魔法感ある。
ただし、「まぁそれはそれとして」的な話もあって、自動ベクトル化効いてくれるケースって本当に単純なループだけなのよね。あとポインタのエイリアシング(=同じメモリを別名経由で触ること)が絡んだり、if文とか複雑な分岐があるとすぐ諦めちゃう。更に言えば配列データが連続じゃない場合もアウトだったり。それだともうしょうがなくて、自分でSIMD命令を直接書いたりアセンブラ弄るしかなくなる。
そういえば、とある開発者さんから聞いたネタなんだけど、「SSE」(128ビット)から「AVX」(256ビット)へ移行した時どうだったか? デスクトップPCだと思ったほど速度アップしなくて「?」となったけど、ノートPCだとかなり良かったらしい。でも理由聞いたら結局デスクトップはRAM帯域がボトルネックだったんだって。つまりベクター幅広げてもメモリアクセス遅かったら意味ないじゃん的な話。
それとね、この後もう一個面白いやつ。「Why Not Both?」的発想もちょっと語りたくなる感じ。(続きはまた今度!)

コンパイラ自動ベクトル化と手動SIMD記述の違いを把握する
最近考えてたんだけど、SIMDとマルチスレッドって別にどっちかだけ使うものじゃなくて、両方同時にフル活用するケースがけっこうある。特に、大きいデータ処理とかでよく見るやつ。CPUの各コアごとに1スレッド割り当てて、それぞれの中でさらにSIMD命令を回す…みたいな。だから並列性は2段階あって、コア(スレッド)単位でも、データ単位でも一気に進めちゃう感じ。
それから、この方式ってNumPyとかIntel MKLとか、高速処理系のライブラリや画像系のフレームワークだとほぼ標準装備なんだよね。とにかく「パラレルできるところは全部並べる」戦略。でもね、大事なのは仕事量がちゃんと多い場合だけ効果的ってこと。小さなタスクの場合は逆効果になることもあって、実際マルチスレッド分けた分だけ無駄が増えるから、むしろSIMDだけゴリ押ししたほうが早かったりする。スレッド立ち上げるコストが意外と無視できない。
思い出したけど、SIMD用のコード書くのって正直言ってだいぶ骨折れる。一方でマルチスレッド化はOpenMPみたいな仕組みをポンっと入れれば、「#pragma omp parallel for」付けるだけでfor文勝手にばらしてくれて本当に楽。「え?これで終わり?」みたいな。
でもSIMD側は…「__m128 a = _mm_load_ps(&array[i]);」みたいな超ローレベル寄りなコード書かなきゃいけないし、行数も地味に増えて見づらいし…。これ初心者には普通によく分かんない領域じゃない?ま、本当それぞれ得意不得意あるから絶対こっち!とは言えないんだけど、とりあえず両方知っといて損はなし。
それから、この方式ってNumPyとかIntel MKLとか、高速処理系のライブラリや画像系のフレームワークだとほぼ標準装備なんだよね。とにかく「パラレルできるところは全部並べる」戦略。でもね、大事なのは仕事量がちゃんと多い場合だけ効果的ってこと。小さなタスクの場合は逆効果になることもあって、実際マルチスレッド分けた分だけ無駄が増えるから、むしろSIMDだけゴリ押ししたほうが早かったりする。スレッド立ち上げるコストが意外と無視できない。
思い出したけど、SIMD用のコード書くのって正直言ってだいぶ骨折れる。一方でマルチスレッド化はOpenMPみたいな仕組みをポンっと入れれば、「#pragma omp parallel for」付けるだけでfor文勝手にばらしてくれて本当に楽。「え?これで終わり?」みたいな。
でもSIMD側は…「__m128 a = _mm_load_ps(&array[i]);」みたいな超ローレベル寄りなコード書かなきゃいけないし、行数も地味に増えて見づらいし…。これ初心者には普通によく分かんない領域じゃない?ま、本当それぞれ得意不得意あるから絶対こっち!とは言えないんだけど、とりあえず両方知っといて損はなし。
両方使う?マルチスレッドとSIMD組み合わせ最適化手法
レジスタ幅、メモリアラインメント、命令のレイテンシ…こういう単語だけでちょっと疲れる。頭の中で「全部覚えないとダメ?」みたいな重圧がある。でも結局、これも慣れだね。最初はよく分からないけど、だんだん慣れてくると「あ、このパターンよくあるやつだ」みたいな安心感あるというか、息ができる感じがする。山登りと似てて、最初はどこまで登ればゴールか分からない。でもコツをつかむと、なんとなく次にどう動けばいいか読めてくる。
あと、SIMDコードはだいたい流れが決まってる。「ロード→並列でごりごり処理→ストア」、これの繰り返し。本当に。最初は難しそうだけど、何回もやってると単純作業みたいになってきたり。
でも一つ勘違いされやすいのが、「レジスタ幅を増やせばそのぶん無条件で速くなる」みたいな期待。でも実際は、そんな単純じゃない。昔のSSE(128ビット)からAVX(256ビット)に移った時、確かにベンチマークとかでちゃんと速くなってた覚えある。でもAVX-512(512ビット)は?となると、思ったほど伸びないというか、場合によっては逆に遅くなってしまうことまであるから不思議。
なんで?理由はけっこう単純で、大きいSIMD命令ほど電力食うし発熱もでかいから。それでCPU(例えばIntel系ね)は、AVX-512使って負荷かけ過ぎると、熱対策でクロック周波数下げちゃうんだよね。「一気にデータたくさん処理できても、そのぶん遅くなる」みたいな現象が起きちゃうから結局トントンだったりする場合もある。本当、原理が分かってくると「あーなるほどな」って意外に納得できちゃう仕組みなんだよなぁ…
あと、SIMDコードはだいたい流れが決まってる。「ロード→並列でごりごり処理→ストア」、これの繰り返し。本当に。最初は難しそうだけど、何回もやってると単純作業みたいになってきたり。
でも一つ勘違いされやすいのが、「レジスタ幅を増やせばそのぶん無条件で速くなる」みたいな期待。でも実際は、そんな単純じゃない。昔のSSE(128ビット)からAVX(256ビット)に移った時、確かにベンチマークとかでちゃんと速くなってた覚えある。でもAVX-512(512ビット)は?となると、思ったほど伸びないというか、場合によっては逆に遅くなってしまうことまであるから不思議。
なんで?理由はけっこう単純で、大きいSIMD命令ほど電力食うし発熱もでかいから。それでCPU(例えばIntel系ね)は、AVX-512使って負荷かけ過ぎると、熱対策でクロック周波数下げちゃうんだよね。「一気にデータたくさん処理できても、そのぶん遅くなる」みたいな現象が起きちゃうから結局トントンだったりする場合もある。本当、原理が分かってくると「あーなるほどな」って意外に納得できちゃう仕組みなんだよなぁ…

書きやすさより効果!SIMDコーディング学習ステップを試す
まず最初に思ったのが、SIMDのレジスタ幅が広くなると、ちゃんと全部データで埋めないともったいないというか…意味なくなっちゃうんだよね。たとえば512ビットのレジスタなら16個詰め込めるけど、実際12個しか使わなかったら残り4つはガラ空きで無駄だし、その余り部分の処理とかも地味に面倒になる。正直、ほとんどのケースだと256ビット(AVX2)がちょうどバランスいい気がする。発熱も少ないし消費電力も抑えられるし、サポートしてるCPUも多いから困らない。
あ、それで意外だけどSIMDってキャッシュとの相性めちゃくちゃ良いんだよね。なんでかっていうと、SIMDレジスタにデータ入れる時って基本まとめてドンッ!て連続したメモリを持ってこれるから。まさしくキャッシュラインやプリフェッチ機能が本領発揮できるパターン。でもマルチスレッドの場合はちょっと事情違ってて、例えばスレッド1と2が同じキャッシュラインAを両方触り始めると、お互い書き換え合戦になってコヒーレンシ暴走みたいになっちゃうことある。そうするとパフォーマンス急降下する。でもSIMDだったら一つのスレッド内だけでやり取り完結できるから、そのコア内ですべて処理できてキャッシュ効率がずっと安定してる印象。特にアルゴリズム側がキャッシュ効率狙って設計されてたりすると、この差かなり大きいと思う。
じゃあいつ使えばいいの?っていうと -
・扱うデータ全部同じ型(float配列とか)になってる場合
・処理内容自体シンプル&分岐少なめ
・メモリ上でデータ配置が連続している
まあ、この3つ当てはまれば基本的には「やろう!」になること多いかなぁ。
あ、それで意外だけどSIMDってキャッシュとの相性めちゃくちゃ良いんだよね。なんでかっていうと、SIMDレジスタにデータ入れる時って基本まとめてドンッ!て連続したメモリを持ってこれるから。まさしくキャッシュラインやプリフェッチ機能が本領発揮できるパターン。でもマルチスレッドの場合はちょっと事情違ってて、例えばスレッド1と2が同じキャッシュラインAを両方触り始めると、お互い書き換え合戦になってコヒーレンシ暴走みたいになっちゃうことある。そうするとパフォーマンス急降下する。でもSIMDだったら一つのスレッド内だけでやり取り完結できるから、そのコア内ですべて処理できてキャッシュ効率がずっと安定してる印象。特にアルゴリズム側がキャッシュ効率狙って設計されてたりすると、この差かなり大きいと思う。
じゃあいつ使えばいいの?っていうと -
・扱うデータ全部同じ型(float配列とか)になってる場合
・処理内容自体シンプル&分岐少なめ
・メモリ上でデータ配置が連続している
まあ、この3つ当てはまれば基本的には「やろう!」になること多いかなぁ。
用途別に最適なSIMD活用タイミングを見極める方法
最近考えてたんだけど、小〜中規模のデータセット、例えば数千とか数百万要素くらいだとどうやって処理する?まず、絶対に実行結果を毎回同じにしたい!って時があるじゃん。で、それなりに最適化はもうしたけど「もっとパフォーマンス絞り出せないかな?」みたいな状況。そういう時SIMDがマジで効くことあるよね。4倍速とか8倍速…下手すればそれ以上?あ、全部スレッド並列しなくても案外OKだったり。
そういえば逆の場合もあってさ。ほんと巨大なデータセット - メモリキャッシュ全然収まらないくらいとか、そもそもアルゴリズム自体が分岐だらけで複雑すぎる場合とかね。その時はマルチスレッド使った方が効果的なパターン多い気がする。両方一緒に使うのもアリっちゃアリ。
要するに、「並列処理」と聞いて即スレッド増やす!って発想はちょっと置いといてほしい感じなんだよね。シングルコア上でも、一つの命令で複数データぶん回す並列性 - これ意外とハマること多かったりして。
あとね、ふと思ったんだけど「実際SIMD、自分で書いたことある?」とか、「普段パフォーマンス上げたい時って真っ先にスレッド増やしてた?」みたいなの、どうなの?自分の場合こうだった、とかあれば聞きたいかも。
そういえば逆の場合もあってさ。ほんと巨大なデータセット - メモリキャッシュ全然収まらないくらいとか、そもそもアルゴリズム自体が分岐だらけで複雑すぎる場合とかね。その時はマルチスレッド使った方が効果的なパターン多い気がする。両方一緒に使うのもアリっちゃアリ。
要するに、「並列処理」と聞いて即スレッド増やす!って発想はちょっと置いといてほしい感じなんだよね。シングルコア上でも、一つの命令で複数データぶん回す並列性 - これ意外とハマること多かったりして。
あとね、ふと思ったんだけど「実際SIMD、自分で書いたことある?」とか、「普段パフォーマンス上げたい時って真っ先にスレッド増やしてた?」みたいなの、どうなの?自分の場合こうだった、とかあれば聞きたいかも。


