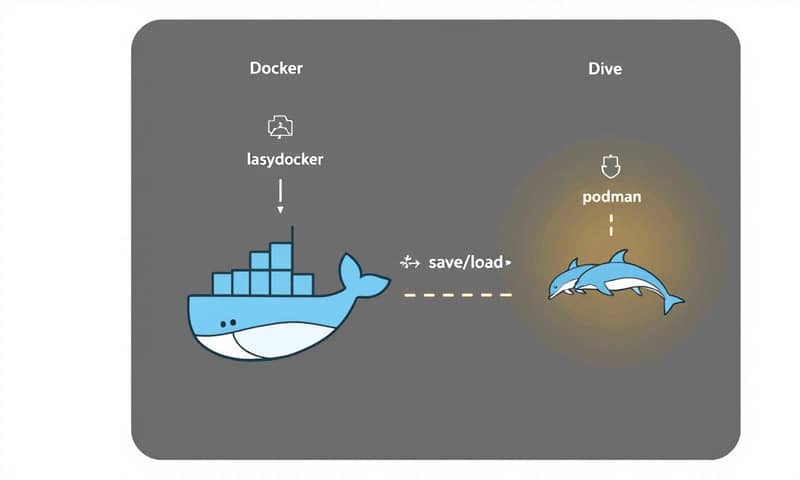最近、DockerやめてPodmanにしようかなって話をよく聞くようになったよね。正直、僕も最初は「また新しいやつか…」って思ってたんだけど、調べてみるとこれがなかなか面白い。特に「root権限なし」で動くとか、「デーモンがいない」とか。でも、一番気になるのはそこじゃないんだよな。
結局、一番大事なのは「今まで使ってたツールがそのまま使えるのか?」ってことじゃない? docker-compose.ymlは? Diveは? DockerSlimは? その辺のリアルな話って、あんまり見かけない気がする。だから今日は、その辺の互換性の話を中心に、僕が実際に試して分かったことを、思考の垂れ流しみたいに書いていこうと思う。
TL;DR
先に結論から言っちゃうと、「全部Podmanに乗り換える必要はない。Dockerと賢く共存するのが今のところ最強」って感じ。Podmanはセキュリティとか軽さとか、Dockerにはないメリットが確かにある。でも、エコシステム、つまり周辺ツールの成熟度はまだDockerに分がある。だから、それぞれの良いとこ取りをするのが一番現実的だって話。
実際のところ、いつものツールは使えるの?
そう、ここが一番の関心事だよね。`podman-compose up`で既存の`docker-compose.yml`が動くってのはよく聞く話。それはまあ、だいたい本当。でも、開発ってそれだけじゃない。イメージの中身を覗いたり、サイズを小さくしたり、便利なUIを使ったり…そういうのができないと、生産性だだ下がりだし。
いくつか代表的なツールで試してみた結果を正直に書いてみる。
Dive: イメージのレイヤーを解析する神ツール
これはね、全く問題なく使える。最高。Docker使ってるときと全く同じ感覚でOK。PodmanはDockerとイメージの保存形式が互換性あるから、ローカルにあるイメージならDiveが普通に読んでくれる。
# まずPodmanでイメージ一覧を見て
podman images
# そのままDiveに渡すだけ。Dockerと違うのは `localhost/` が付くことが多い点かな
dive localhost/my-app-imageこれでいつも通り、どのレイヤーでファイルが増えてるかとか、無駄なファイルがないかとかをチェックできる。これは本当に助かる。
DockerSlim: イメージを自動でスリムにしてくれる魔法
うーん、これはね、直接は使えない。これが結構痛い。DockerSlimはDockerのAPIソケット (`/var/run/docker.sock`) に接続することを前提に作られてるから、デーモンレスなPodmanだと「接続先がいないよ!」って怒られちゃう。
じゃあ諦めるしかないのか?っていうと、そうでもない。ちょっと面倒だけど、回避策はある。
- Podmanでビルドしたイメージを `podman save` でtarファイルに書き出す。
- そのtarファイルを `docker load` でDockerに読み込ませる。
- Docker側でDockerSlimを実行して、イメージをスリム化する。
- スリムになったイメージを `docker save` でまたtarファイルに書き出す。
- 最後に、そのtarファイルを `podman load` でPodmanに読み込む。
…正直、面倒くさいよね。でも、本番環境にデプロイするイメージを極限まで小さくしたい、っていう需要は確かにあるから、この手順を知っておく価値はあると思う。後で具体的なコマンドも紹介するよ。
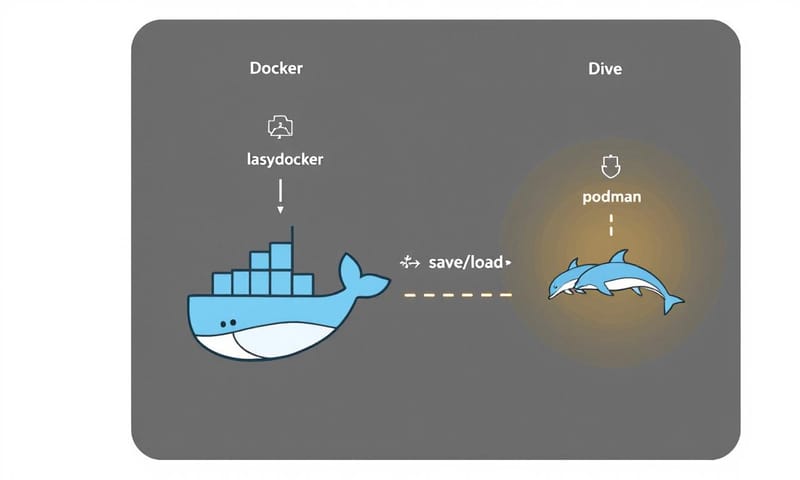
Lazydocker / Dockge: CUIやWeb UIの管理ツール
これもDockerSlimと同じ理由で、基本的には動かない。LazydockerもDockgeも、Dockerソケットに依存してるからね。PodmanにはPodman Desktopっていう公式のGUIがあるけど、ターミナルでサクッと操作したい派からすると、Lazydockerが使えないのは地味に痛い。
これも「じゃあ開発中はDocker使って、本番運用はPodmanで」みたいな使い分けが現実的になってくる理由の一つかな。無理に全部Podmanでやろうとすると、こういうところでストレスが溜まっちゃう。
じゃあ、どうやってPodmanを始めるの?
互換性の話ばっかりしちゃったけど、実際に導入する手順ももちろん大事。ここはOSによってちょっと違う。特にMacは一手間いるから注意が必要。
Linux (Ubuntu/Debian系) の場合
これは一番簡単。パッケージマネージャで一発。
sudo apt update
sudo apt install podman
# podman-composeも忘れずに。pipで入れるのが一般的かな
pip3 install podman-compose最近は`podman compose`っていう、`podman`コマンドに統合されたバージョンもある。`podman-compose`はPython製の別ツールで、`podman compose`はGoで書かれててPodman本体に含まれてる。どっちを使えばいいか迷うけど、今から始めるなら公式に統合された`podman compose`の方を意識していくのが良さそう。Podman Desktopを入れるとこっちが入ったりする。
Macの場合 (Homebrew使用)
MacはLinuxと違って、コンテナをネイティブに実行できない。だから、裏側で軽量なLinux仮想マシン(VM)を動かして、その中でコンテナを走らせる仕組みになってる。Docker Desktop for Macがやってることと、基本的には同じだね。
# まずはpodman本体をインストール
brew install podman
# これでPodmanのVMを初期化して起動する
podman machine init
podman machine startただ、これを実行しただけだと、Docker APIとの互換性が完全じゃないことがある。ターミナルに「`podman-mac-helper`をインストールするといいよ」みたいなメッセージが出るはず。それに従うのが吉。
# たぶんこんな感じのコマンドを実行するように言われるはず
sudo /opt/homebrew/Cellar/podman/<バージョン>/bin/podman-mac-helper install
podman machine stop
podman machine startこれをやっておくと、Docker APIのエンドポイント(ソケットファイル)がDocker Desktopと同じ場所 (`/var/run/docker.sock`) に作られて、Dockerにしか対応してないツール(の一部)がそのまま動くようになったりする。まあ、それでもLazydockerとかはうまく動かなかったりするんだけど…。やっておいて損はない設定かな。

DockerとPodmanを共存させる「賢い」使い方
ここまで読んで、なんとなく察しがついたかもしれないけど、僕がおすすめしたいのは「Podman原理主義」になるんじゃなくて、「Dockerのエコシステムも活用しつつ、Podmanのメリットを享受する」っていうハイブリッドなスタイル。
そのための鍵になるのが、さっきちょっと触れた `save` と `load` コマンド。
例えば、さっきのDockerSlimみたいに「Podmanでは直接使えないけど、Dockerなら使える」ツールを使いたい時。こんな感じでイメージを行き来させることができる。
-
PodmanからDockerへイメージを渡す
まずPodmanで開発・ビルドしたイメージをtarファイルにエクスポートする。この時、Podmanのイメージ名には`localhost/`が付いてることが多いから、それを忘れずに指定するのがポイント。
# Podmanからイメージをtarファイルとして標準出力に書き出す podman save localhost/my-flask-app > my-flask-app.tar # Docker側で標準入力からtarファイルを読み込む docker load < my-flask-app.tar -
Docker側でよしなにやる
Dockerにイメージが来たら、こっちのもん。DockerSlimで軽量化するなり、他のDocker専用ツールで何か処理をするなり、自由にできる。
# Docker側でDockerSlimを実行 docker-slim build my-flask-appこれで `my-flask-app.slim` みたいな軽量化されたイメージが出来上がる。
-
DockerからPodmanへイメージを戻す
処理が終わったら、逆の手順でPodmanに戻してあげる。
# Dockerからスリム化されたイメージを書き出す docker save my-flask-app.slim > my-flask-app-slim.tar # Podmanでそれを読み込む podman load < my-flask-app-slim.tar
これで、Podmanのrootlessな環境で、Dockerツールで最適化されたイメージを動かせるわけだ。このワークフロー、ちょっと手間はかかるけど、知ってるとめちゃくちゃ便利。 CI/CDパイプラインに組み込む時も、ビルドステージではDockerを使いつつ、デプロイステージではPodmanを使う、みたいな分業が可能になる。
結局、どっちを使えばいいの?比較してみた
じゃあ、改めてメリット・デメリットを整理してみようか。まあ、僕の個人的な感想マシマシで。
| 比較ポイント | Docker | Podman |
|---|---|---|
| 根本的な違い | デーモン(常駐プロセス)が必要。API経由で操作するクライアント・サーバーモデル。 | デーモンレス。コマンド実行時にプロセスが起動する。fork/execモデルでLinuxの作法に近い。 |
| セキュリティ | デフォルトではroot権限が必要。Dockerソケットの権限管理は結構気を使うよね…。 | Rootless(ルート権限不要)が基本! これが最大のメリット。一般ユーザー権限で完結するから安心感が全然違う。 |
| CLIの互換性 | まあ、こっちが元祖だからね。 | `alias docker=podman` でだいたい動くように作られてる。たまに動かないオプションもあるけど、9割方いける印象。 |
| Compose機能 | `docker compose` (v2)。成熟してて、機能も豊富。文句なし。 | `podman compose` がある。`docker-compose.yml`を読めるけど、Docker Composeの高度な機能(例えば`profiles`とか)の一部は未対応だったりする。要注意。 |
| 周辺ツール (エコシステム) | 圧勝。Lazydocker, Dockge, DockerSlim…便利なツールはだいたいDockerありき。これが乗り換えを躊躇させる一番の理由かも。 | 正直まだ弱い。Diveみたいに汎用的に使えるものもあるけど、多くは`docker save/load`のブリッジが必要。今後に期待。 |
| Kubernetes連携 | Docker DesktopにKubernetes機能はあるけど、ちょっとおまけ感。 | `podman generate kube` でPodから直接KubernetesのYAMLを生成できる。思想的にこっちの方がK8sと親和性高い。Red Hatが作ってるだけある。 |
| システム連携 | コンテナをサービスとして自動起動するには、自分でsystemdのunitファイル書いたり、再起動ポリシーを設定したり。 | `podman generate systemd` でコンテナ用のunitファイルを自動生成できる。システムサービスとして扱いたいなら、こっちが圧倒的に楽。 |
まとめ:僕なりの付き合い方
というわけで、色々見てきたけど、今の僕の結論はこう。
- ローカルでの開発・試行錯誤フェーズ: 便利なUIツールとか使いたいから、まだDockerが優勢。Lazydockerなしでは生きていけない体になっちゃってるし…。
- CI/CD パイプライン・本番環境: セキュリティと安定性が最優先。だから、PodmanのRootlessモードが輝く。コンテナをsystemdで管理できるのも、運用を考えるとすごく魅力的。
だから無理にどっちか一つに絞るんじゃなくて、「開発時はDocker、デプロイはPodman」みたいに使い分けるのが、一番ストレスなく、かつ安全な方法なんじゃないかな。そのための`save`/`load`テクニックだしね。
日本の開発コミュニティ、例えばQiitaとかでもPodmanの記事はすごい勢いで増えてる。でも、みんながみんな一斉に乗り換えるというよりは、こういう現実的な共存方法を探ってる段階なんだと思う。まあ、Red Hatが本腰入れて開発してるから、これからエコシステムがどんどん追いついてくる可能性は十分ある。その時が来たら、また考えればいいかなって。

結局のところ、コンテナ技術の未来は、より安全で、よりLinuxの作法に忠実な方向(つまり、RootlessでDaemonless)に進んでいくはず。Podmanはその流れを先取りしてる。だから、今から触っておいて、その思想に慣れておくのは絶対に無駄にはならないと思うな。
ところで、みんなはもうPodman使ってる?それともまだDocker派?
もしPodmanに移行して「このツールの互換性でハマった!」とか、「こんな裏技で解決したよ」みたいな話があれば、ぜひコメントで教えてほしいな。情報交換したい!