この移動平均線、ちょっとヤバいんだけど
デイトレとかスキャやってると、結局テクニカル指標から逃げられないじゃん。で、たいてい最初に出てくるのが移動平均線。SMA とか EMA とか、とりあえずチャートに3本ぐらい出して「それっぽく」してみるやつ。
でもさ、5つもインジ入れて、条件20個ぐらい並べて、「全部そろったらエントリー!」みたいなやつ、正直もう疲れない?
今回のは、そういうのにうんざりしてる人向けのやつ。
名前がちょっとカッコつけてて DEMA Oscillator(ディーマ・オシレーター) って言うんだけど、その中で使う手法を、ここでは便宜上 Dimma オシレーター戦略 って呼んでいくね。
ざっくり言うと、「ごちゃごちゃしたノイズを削って、上か下かをハッキリ見せてくれる」系のインジ。買いと売りのサインも、色と位置だけでかなり直感的に分かるようになってる。
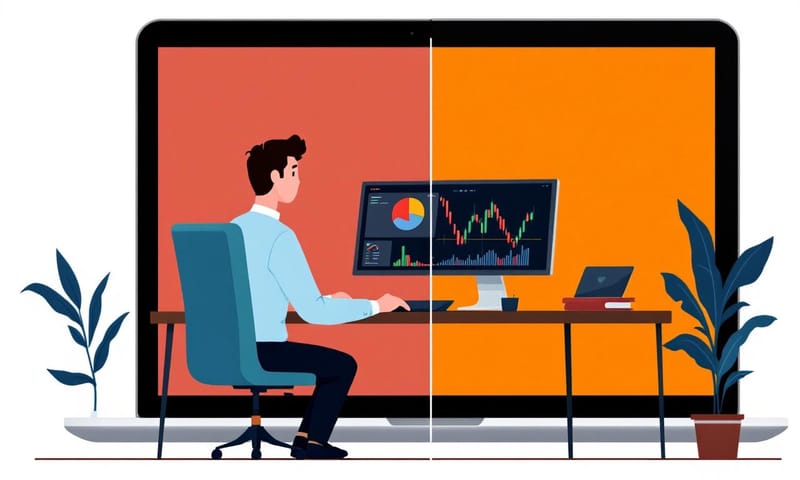
Dimma(DEMA)オシレーターってそもそも何者?
前に読んだ海外トレーダーの記事で知ったんだけど、DEMA Oscillator って、普通の「移動平均線」よりもう一歩踏み込んだモメンタム系のインジで、ベースになってるのが DMA(Displaced Moving Average) っていう「ちょっとズラした移動平均線」なんだよね。
DMA を2本使って、その差をオシレーターとして下段に表示してくれる感じ。で、その値が ゼロラインをまたぐかどうか がけっこう大事になってくる。
雰囲気としては、MACD のヒストグラムと RSI の中間くらい。だけど、DMA ベースだから、ラグ(遅れ)を抑えつつ、急なモメンタム変化もそこそこ拾ってくれる、っていうイメージに近いかな。
ゼロラインを上に抜けたら「上方向の勢いが優位」、下に抜けたら「下方向の勢いが優位」。この単純な切り替わりが、スキャルとか短期の逆張り・順張りで結構使える。
TradingView でのセットアップ、めちゃ単純
インジ探すのめんどいと、そこでやる気なくなるタイプなんだけど(笑)、これは設定手順がシンプルだからまだマシ。
TradingView 開いて、通貨ペアでも株でもいいから 5分足チャート 出す。
上のバーから 「インジケーター」 をクリック。
検索窓に 「Dema Oscillator SD」 って打ち込む。
候補の中から 「Normalized Dema Oscillator SD」 を選択。
これで、チャートの下にオシレーター、ローソク足の上にはバンドっぽい線が出てくるはず。よく使いそうなら、お気に入りにピン留めしておくと楽。

買いのパターン、条件をざっくり並べると
細かく言い出すと枝葉が増えるから、まず「最低限これだけはそろっててほしい」という条件だけ書くね。
オシレーターがゼロラインを上抜け
下にいた波形が、ゼロラインをまたいで上側に出てくる。これで一応「上方向のモメンタムが優勢になってきた」というサイン。ローソク足の色が赤 → 青に変わる
このインジ、ローソクの色も変えてくれるタイプなんだけど、売り圧が強いときは赤、買いが優勢になると青、みたいな感じになってるはず。赤の流れから青に切り替わる瞬間がひとつのヒント。今のローソク足が Dimma バンドの「上側」にいて、しかも触ってない
バンドの上にローソクが乗ってるけど、ぴったりくっついてはいない。ちょっとだけ余白がある。 これが、伸びきったところをつかんでるんじゃなくて、「まだ余裕を残して伸びる可能性がある」状態の目安になる。
で、損切りと利確はこんな感じのイメージ。
📍 ストップ(損切り) → Dimma の下側バンド に置く。 🎯 ターゲット → おおむね 1:1.5 のリスクリワード を狙う。
例えば、ストップが10pips なら、利確は15pips 前後を基準にする感じ。
売りのパターンは、ほぼ逆をイメージすればOK
ショート側は基本的にさっきの逆。
オシレーターがゼロラインを下抜け
上側にいた波形が、ゼロラインを割り込んで下に出る。これで下方向のモメンタム優勢。ローソク足の色が青 → 赤に変わる
さっきまで買いがんばってたのが、急に売り側に主導権が移ったサイン。今のローソク足が Dimma バンドの「下側」にいて、かつ触ってない
バンドの下に、少し距離を空けてローソクが出ている状態。これも「まだ伸びしろがありそうな下落」を狙いにいくイメージ。
ストップとターゲットはこんな感じで使い分けるとちょうどいいかも。
📍 ストップ → やっぱり Dimma のバンド側 に置く。 🎯 ターゲット → 1:1 〜 1:1.5 あたり。
トレンドが強いときは 1:1.5 まで引っ張るのもアリだし、ちょっと怪しいレンジ気味なときは 1:1 でさっさと抜ける、みたいに使い分けてもいい。
バックテストのやり方、面倒だけどここサボると全部ブレる
どんな手法も、「チャートのスクショ見てるだけ」の時点ではだいたい良さそうに見えるんだよね…。だからこそ、最低限のバックテストはやったほうがいいやつ。
TradingView 使う前提で、流れだけ書いておく。
5分足チャートを開く
通貨ペアは後で触れるけど、とりあえず EUR/USD でも GBP/USD でもいい。Normalized Dema Oscillator SD を追加
さっきの手順でインジを表示させておく。チャートを過去にスクロールして、自動スクロールを切る
右下あたりの「自動スクロール」みたいなチェックを外して、ある程度前の日付まで戻っておく。バーリプレイ(Bar Replay)モードを使う
上のツールバーから、過去のある時点を選んで、そこから一個ずつローソクを進めていく。エントリー条件を満たしたポイントだけをピックアップ
・オシレーターがゼロラインをクロスしたか ・ローソクの色が切り替わったか ・ローソクの位置がバンドに対してどうなっているか みたいなのを一個ずつ見ながら、「ここならルール的に入るな」というところだけチェックしていく。トレード記録をつける
・エントリー価格 ・ストップ(どのバンドを基準にしたか) ・利確(1:1 or 1:1.5 のどっちを選んだか) ・結果が勝ちか負けか をメモ帳でもスプレッドシートでもいいから書いておく。
自分が前に読んだ統計の話だと、こういうルールベースの手法って、最低でも 50 トレード、できれば 100 トレード前後 は試さないと、「たまたま調子よかった期間」を見て勘違いするリスクがかなり高くなるって言われてた。
50〜100 回ぐらい回すと、「勝率がだいたいどのくらいか」「連敗するときどれくらい続きそうか」「1ヶ月やったときに資金カーブがどんな形になるか」みたいなイメージがつかめてくるから、そこまではちょっと頑張ってみてもいいかも。

どの銘柄・どんな相場で使うとマシか
こういうモメンタム系のインジは、そもそも「動いてくれないと話にならない」タイプなので、レンジのど真ん中で使うとほぼ無意味に近い。
よく名前が出てくるのは、例えば:
EUR/AUD
GBP/USD
EUR/JPY
みたいな、そこそこボラがあって、スプレッドも極端に広くないメジャー通貨ペア。 日本だと、国内業者より海外口座でやってる人も多いけど、レバ規制とか約定力とか、そこはもう完全に個人のスタイルとリスク許容度次第。
あと、さっきもチラッと触れたけど、レンジ相場は基本避けたほうがいい。ブレイクの方向感が出てるときとか、トレンドが出ているときのほうが、このオシレーターの「ゼロライン・クロス」がちゃんと意味を持ってくれる。
で、これ地味に大事なんだけど、ローソク足がバンドにベタッと触ってるときは、基本エントリーしないほうがいい。 伸び切ってからの「最後の一伸び」を取りにいこうとして、だいたいその直後に反転してやられるパターン、結構あるから。
リスク管理の話も一応書いておくと、一般的な海外のトレード本とかだと、1トレードあたり口座資金の 1〜2% まで をリスクにするのが標準ラインってよく書かれてる。 日本語の投資本でも、同じくらいの数字を推してる人が多い印象。
このくらいにしておくと、連敗しても「一発退場」にはなりにくいから、精神的にもまだ耐えられるゾーンに収まりやすい。
他のツールと組み合わせるときの考え方
Dimma だけでも売買ルールは作れるんだけど、もう少し「根拠を積み上げたい」タイプの人もいると思うから、よく一緒に使われがちなものもメモしておく。
ボリューム系(出来高)
海外勢は Volume Profile を好んで使ってる印象あるけど、「そのタイミングでちゃんと出来高も増えてるか」を見て、ブレイクが本物っぽいかどうかをざっくりチェックするのに使える。EMA(20 とか 50)
トレンドの方向性をざっくり決めるフィルターとして、「ローソクが EMA20 より上にいるときは買いだけ見る」「下にいるときは売りだけ見る」みたいな使い方が多い。 こうすると、逆張りの変なエントリーを少し減らせる。サポレジ・価格帯ゾーン
直近の高値・安値とか、何回も止められてるラインの近くで Dimma のサインが出たら、「そこを抜けるブレイクなのか」「跳ね返されるのか」を意識して見る。 自分の中で、「サポレジに近いときはリスクリワードをどうするか」とかも決めておくと、後で迷いにくい。
正直なところ、自分ならこう扱うかな…
個人的には、どんなインジも「これだけ見れば勝てる」みたいな扱い方をし始めた瞬間に、だいたい崩れると思ってて。
Dimma みたいなオシレーターも、「モメンタムの切り替わりをちょっと早めに教えてくれる補助ツール」くらいの立ち位置で見ておくほうが、長く付き合える気がする。
特に短期だと、感情が一番の敵 みたいなところあるから、 ・色で方向をざっくり教えてくれる ・ゼロラインで ON/OFF が分かりやすい ・バンドでストップ位置の目安も作れる っていう、この3つがそろってるだけでも、判断の負担はかなり減るんじゃないかなって感じてる。
ただ、その代わりというか、やっぱりバックテストとトレード日誌はセットでやったほうがいい。 海外のトレード教育系の記事でも、日本の投資本でも、最終的に残ってる人はだいたいそこに落ち着いてる印象あるし。
じゃあ、どう使い始めるのが現実的か
いきなりリアル口座で全力っていうのは、まあ普通にキツいから、流れとしては:
TradingView で Dimma 入れて、まずは チャートを眺める期間 を作る
そのあと バーリプレイで 50〜100 トレード分 のバックテスト
次に、デモ口座 or 超少額ロット で同じルールを回してみる
トレード日誌に、感情とかミスも含めて ぜんぶ書いていく
このあたりまでやって、「あ、なんとなくこのインジのクセ分かってきたな」と思えたら、そこからロットを少しずつ上げていく、くらいがちょうどいい気がする。
マーケットは時期によってボラも変わるし、トレンドの出方も違うから、ある月はすごく相性が良くて、別の月はぜんぜんダメ、みたいなことも普通にある。 だからこそ、一時的な結果より、「ルールを守れたかどうか」をちゃんと見ておくのが、結局いちばん大事になるのかなって思う。
ここまで読んで、「これちょっと触ってみようかな」と思った人は、 ・まずはどの通貨ペアでやるか ・1トレードあたり何%までリスクを取るか ・1:1 と 1:1.5、どっちを基準にするか この3つだけでも、ノートかメモアプリに書き出してみてほしい。
で、もし実際に試してみたら、「Dimma ここが好き」「ここがイマイチだった」みたいなの、どこかに書き残しておくと、数ヶ月後に読み返したときけっこう面白いよ。


